変化に即した対応を進める ―― ニチレイ・大櫛社長

ニチレイ大櫛顕也社長は10日、東京・築地の同本社で年末会見を行った。大櫛社長は、現況を「世界情勢は混沌としている。自然災害に加え、取り巻く環境は変化をし続けている。今なお円安傾向は続いており、調達面への影響を引き続き注視していくとともに、変化に即した対応を進めていきたい」とし、上期の増収増益を踏まえ、「通期売上高7000億円、営業利益405億円を見込んでいる。売上高、営業利益ともに達成すれば、いずれも過去最高を更新する、計画達成を目指していきたい」とし来期に向けた施策を述べた。
来期に向けた施策要旨は以下の通り。
収益性の向上に関しては、コストアップへの対応として、生産性改善などの自助努力を基本とし、それを超えるものについては価格改定を実施していく。 来年の2月から家庭用、業務用冷凍食品の改定を行う。
一方、販売数量の増加に向けては、ニチレイフーズの米飯類、チキン加工品といった戦略カテゴリーや、個食麺などのパーソナルユース商品を拡販。
ニチレイフレッシュは従来から取り組んでいる「亜麻仁の恵み」「ぷるるん生えび」など、だわり素材やMSC認証の水産品の拡販を推進していく。
ニチレイロジグループは、2024年問題を契機とし、運送需要が全国で大きく伸長している。冷食プラットフォーム構築に向けて、次世代輸送システムであるSULS(サルス)やゲートウェイ機能の拡充を進めていく。
海外事業に関しては、まずニチレイフーズの北米事業で、新しくラテンブランド商品の販売を開始。ニチレイフレッシュは、ベトナムのTPSに新たな加工ラインと冷蔵庫を増設した。ニチレイロジグループもオランダ、イギリスの組織再編を実施することで、迅速な意思決定ができるようにした。またポーランドに冷凍物流センターを増設、ベトナムでも新たな低温物流センターが稼働し、欧州とASEANにおける低温物流ネットワークを拡大、今後も引き続き食品事業、物流事業とも海外事業の推進を加速していく。
今中計「Compass Rose 2024」ではサステナビリティ経営の加速を挙げ、環境と調達に関する課題を優先的に取り組んでいる。TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の取り組みに賛同し、各事業の自然資本や生物多様性におけるリスクや機会への対応強化を進めている。その結果を受け、水資源を含む生物多様性に関して目標へ追加した。カーボンニュートラルの実現に向けては、自社拠点への太陽光発電パネル設置や、オフサイトPPAサービスの導入を進めている。
来年12月1日で、創立80周年を迎える。そして来年度は新しい中期計画がスタートする。また、ニチレイフーズフレッシュの機能再編を予定している。北米子会社の統合管理を皮切りに、調達から販売までの全ての大きなを機能を見直し、食品事業の統合に向けた機能再編を進めていく。
米国・カニカマ工場竣工 ―― 極洋

初年度3000tを生産
極洋は10日、米国の同社連結子会社Oceans Kitchen Corporation(米国・ワシントン州ケント市、加藤穣社長)が同州に整備を進めていたカニ風味かまぼこ製造工場を現地の9日に竣工したと発表した。
カニ風味かまぼこは、米国でサラダやカリフォルニアロールの具材として都市部を中心に親しまれている。健康志向の高まりから高たんぱく質・低カロリーな食材として、注目されて、今後はローカルエリアへの浸透などにより、更なる消費の拡大が見込まれる。また、主原料のスケソウダラすり身はアラスカが一大生産地であり、この地に近い同州に工場を設立した。キョクヨーフーズ㈱(愛媛県)では、カニ風味かまぼこを40年生産してきた実績を持ち、その生産のノウハウを生かし、米国での用途や嗜好に合わせた米国仕様品を生産していく。
同工場は敷地面積2万5517㎡、延床面積7214㎡。生産品目は業務用・市販用のかに風味かまぼこ(冷凍・チルド)。初年度生産能力は約3000t。従業員数は20名(25年度)。投資額は約2500万ドル(約37億円)。12月にテスト稼働。来年1月から本格稼働する予定。
日中の更なる関係強化誓い合う ―― 日中凍菜安全会議

中国、響水県で開催した日中冷凍野菜安全会議
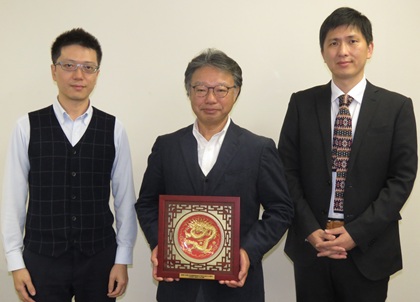
記念の盾を持つ中井会長(中央)、髙橋事務局長(右)、凍菜事務局楊爽氏(左)
輸入冷凍野菜品質安全協議会(凍菜協・中井清典会長)は5日、都内で「日中冷凍野菜品質安全会議報告会」を開き、11月22日に中国・響水県において中国食品土畜進出口商会(土畜商会)と開催した「日中冷凍野菜品質安全会議・懇親会」の進捗と成果などついて、中井会長、髙橋健二事務局長が報告した。
凍菜協と土畜商会が中国で品質安全会議・懇親会を開催するのは2019年以来5年ぶり。今回の会議は、日本側の消費者団体代表も招待し、生活者に中国産冷凍野菜の品質の安全性の高さについて知ってもらう場としても活用している。日中冷凍野菜品質安全会議には、日本側から35人、中国側から113人(計148人)が参加した。
安全会議は、干露土畜商会副会長、中井会長の代表者挨拶で開会し、開催地である響水県を代表して郭超書記が祝辞を述べた。中井会長は凍菜協について①品質管理基準評価の実施、認定②中国パートナー企業との共同会議開催③残留農薬技能試験の技術向上④残留農薬管理に必要なガイドラインの策定・実施─などを中心に活動していると説明。凍菜協と土畜商会の共同の取り組みなどによって、2023年の中国からの輸入冷凍野菜の違反件数が2010年比で半減していると中国側に感謝を述べた上で、農薬散布のドリフト問題や異常気象の状態化など新たな問題も起きているとして、引き続き日中の密接な連携で様々な課題を克服し、日中の冷凍野菜流通を更に発展させたいと呼びかけた。
引き続き、佐々木菜保子在中国日本大使館経済部一等書記官による「ポジティブリスト制度への対応及び直近の輸入検査違反状況について」、徐棟土畜商会冷凍野菜分解理事長による「税関による中国輸出冷凍野菜の監督管理について」の2講演を開催。金子茂靖凍菜協副会長が日本における輸入冷凍野菜の課題について中国側に説明し、山本純子氏が冷凍野菜のトレンドについて講演した。同会では、凍菜協からの発案として、日中で新たに「品質技術部会」を立ち上げて、様々な課題解決に向けて連携していくことを提案した。また、凍菜協が設立20周年を迎えることから、中国側に記念品も贈呈。日中が活発に情報交換する盛会となった。
翌23日には、日中の出席者一行が冷凍ブロッコリーなどを製造する響水県の「万銀食品」を視察。広大な圃場と安全管理を徹底した同工場の製造工程などを見学した。
報告会で説明に当たった中井会長は「日中の懇親会は5年ぶりの開催で、日本側、中国側共に参加するメンバーも変わった。そのような中で、中国側に万全の準備で出迎えて頂き、圃場や工場なども視察する有意義な会となった。凍菜協としても、新体制の下で今後の方向性が定まり、今後に繋がる会となったと感じている」としている。